
加藤登紀子と六角精児との対談は、特別コンサート『加藤登紀子のフォークソングに乾杯!~戦後80年、戦争を知らない子どもたちへ~』(8月16日に東京・有楽町よみうりホールで開催)に六角がゲストとして出演することを受けてのものである。このコンサートは、フォークソングの魅力を伝えると同時に、歌を通して平和の大切さについて考える機会を提供するとの趣旨がある。六角以外のゲストは、トワ・エ・モワ、Yae(ヤエ)、白鳥マイカで、加藤登紀子とトワ・エ・モワはフォークソング・ブームを牽引した世代、Yaeと白鳥マイカはフォークソングの精神を受け継ぐ世代である。俳優の六角精児はその中間の世代と言えるだろう。彼自身も六角精児バンドの一員として精力的に音楽活動を行っており、フォークソング・マニアとしても知られている。実はこの対談の直前に行われた打ち合わせが、二人の初顔合わせだった。しかし、とても初対面とは思えないほど率直で活気あふれるトークとなった。フォークソング、平和、路上など、テーマが自在に往き来する対談を前後編でお届けする。
──今回のコンサートは、会場内全体でその“パワー”を共有する場になりそうですね。
加藤それぞれのフォークソングがゴボッと出てきたということは、その歌にパワーがあったということなんですよ。ところが時が経つと、いつの間にか、「あの頃のヒット曲ですよね。懐かしいメロディですね」ってことで、ないまぜにされるじゃないですか。そうではなくて、なぜゴボッと出てきたのか、そのパワーとその背景を少しでも感じてもらいたいというのが『フォークソングに乾杯!』の狙いですね。

六角自分たちは、音楽の流れとして見た上で、“これがフォークだ”と認識していましたが、一人ひとりのモチベーションがわからないと、理解しづらいところはあるかもしれませんね。
加藤シンボリックに言うと、ミュージシャンが貧乏だった時代はギターの弾き語りだったんですが、豊かになってくると、ピアノに変わるわけ。その前までは、路上に車座になって座れる感じ、路上とふれられる感じが当時のフォークソングにはありました。
六角当時の写真を見ても、ヒッピーが地面に座っていたりしますもんね。
加藤それがカーテンのある部屋で、ピアノを弾いている風景になり、生活スタイルの変化が音楽にも反映し、フォークからニューミュージックへ、さらにJ-POPへと移り変わっていきました。世につれるのが音楽だから、それは悪いことではありません。でも、受け継いでいくべきことはあるんですよ。六角さんは私と年齢がかなり違いますが、あの当時の路上感を持っているところが同じだなと思いました(笑)。
六角えっ、路上感ですか(笑)。ありますか?
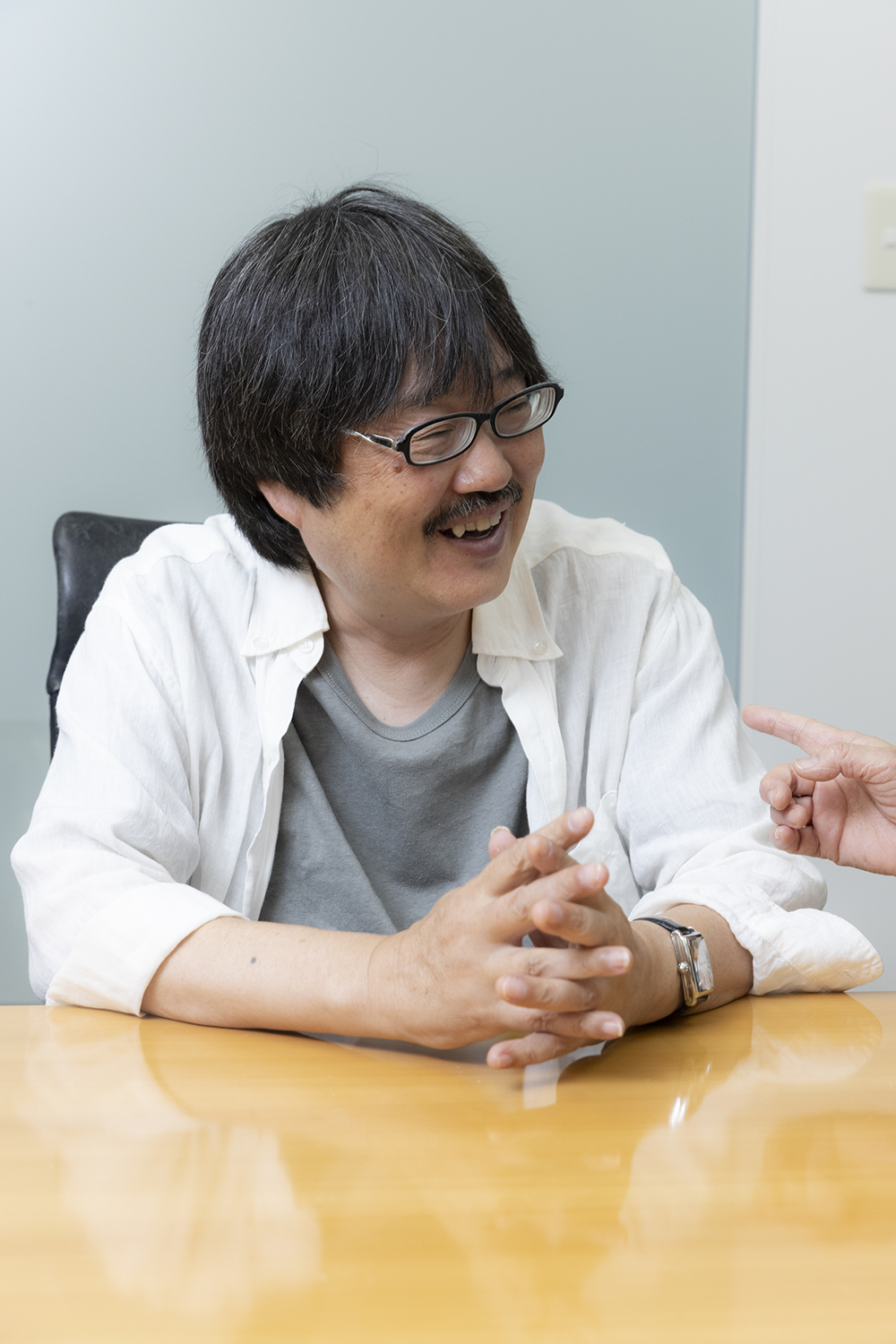
加藤路上感のある人って、昭和の時代にはたまにいたんだけど、六角さんの世代では珍しいわよね。西田敏行さんとか、渥美清さんとか、そういう人って、世の中に必要なんですよ。
六角路上感という表現、僕は初めてされました(笑)。
加藤路上感があるというのは、風雪に耐え、過酷な環境の中でも生きていく力があるということですよ。

──幼少期からフォークソングを聴いていたことによって、育まれてきたものかもしれないですよね。
六角でもやはり、当時の感覚とは違いますよね。僕も含めてですけど、今の若い人たちが60年代後半のフォークソングを聴いて感じ取っていることって、その頃のニュアンスとは少し違うのかもしれないと思うんですよ。でもそうした違いがあった上で、自分は自分で、1960年代の歌に自分の気持ちを乗せて自分の歌を歌う、そして本物の方がいらっしゃって歌う、そういう幅みたいなものがあっても、おもしろいのかなと思います。
加藤わからなくても、わかろうとするまなざしがあることが素晴らしいことですよ。今回のコンサートのテーマとも関係しますが、北山修さんが『戦争を知らない子供たち』というエッセイを出版していて、その中に、なぜ「戦争を知らない子供たち」という曲を作ったかが書かれているんですね。たまたま米兵と飲んだ時に、別れ際に相手が、「明日戦争に行ってくるよ」と言ったことがきっかけになったとのことでした。今はありませんが、当時のアメリカは兵役がありました。その時に、自分たちは戦争を知らない世代として生まれて、兵役のない国、戦争をしないと決意している国に生きているんだと気付いたことから生まれた曲だと、北山さんが書かれていました。私はこの曲を10年くらいまえに北山修さんと一緒に歌ったことがあるのですが、その時にも、改めて戦争をしないという憲法を持っていることのかけがえのなさを感じました。戦後80年間、よくこの憲法を改正せずに持ちこたえたなと思いますし、そのことを高らかに歌い続けることをコンサートのテーマとしたいんですよ。
六角僕らの小学校の時のソングブックにも「戦争を知らない子供たち」が掲載されていましたし、当たり前のように歌っていました。でも、なんの自覚もなく、普通にいい歌だなと思って歌っていました。でも、あちこちで戦火が上がっている時代だからこそ、この歌を歌う意味があるんだなと思いました。

──お二人の話をうかがっていて、音楽という形で共有していくこと、受け継いでいくことの大切さを感じます。曲が生まれた当時の思いがすべて伝わらなかったとしても、どこかのタイミングで、誰かに伝わる可能性があることも、音楽の素晴らしいところですよね。
加藤サトウハチローさんが広島の原爆で死んだ弟のことを思いながら歌詞を書いた「悲しくてやりきれない」という曲を、みんなが手を繋ぎながら微笑みを浮かべて歌っていたりするじゃないですか。でもそれはそれでいいんだと思います。だって、歌ってそういうものだから。その歌の背景にまで踏み込まなくてもいいし、踏み込んでもいいし。
六角すごく乱暴な言い方になりますが、歌は、なんでもいいと思うんですね。だからこそ、なんでも良くないと思う人がいてもいいんですよ。自由に発信できるし、自由に受けとめられる。そこがいいのかなと思います。
加藤私もそうだし、北山修さんとかフォークの人たちがダイレクトに表現するのは、少し照れくさいと思うところもあるわけ。ザ・フォーク・クルセダーズの「帰って来たヨッパライ」のプロモーション映像があって、<オラは死んじまった>というフレーズのところで、ベトナム戦争で亡くなった米兵が一人ずつ、天国の階段を上るアニメで描かれているのね。
六角かなりブラックですね。
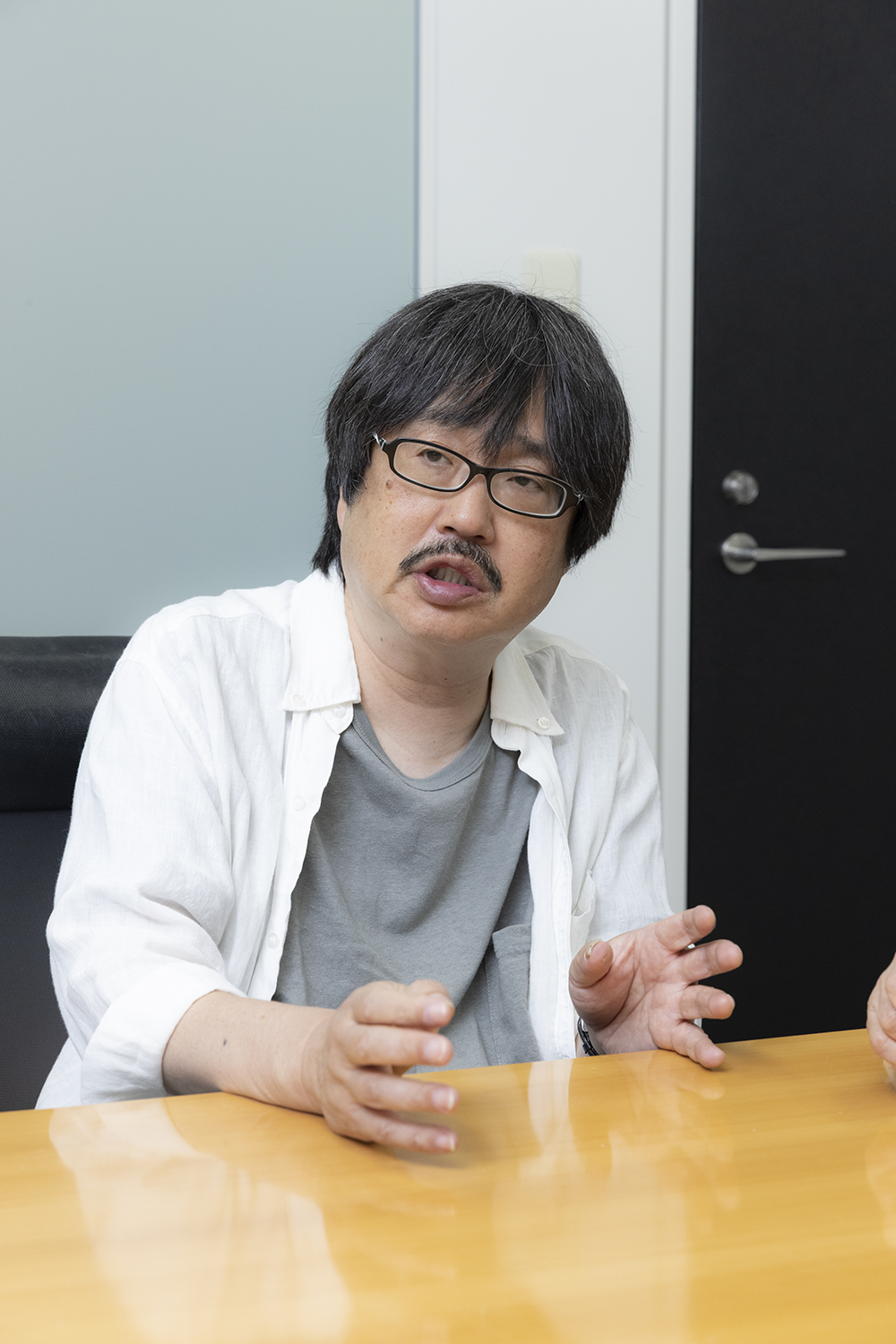
──当時はコミックソング的な受け取り方もされていました。
加藤その映像に関しては、北山さんもとくに説明されていないので、それぞれに受け取り方があるでしょうし、それでいいと思うんですよ。
──ザ・フォーク・クルセダーズの「悲しくてやりきれない」も、近年、映画『この世界の片隅に』のオープニングテーマとしてコトリンゴさんが歌っていますし、加藤さんもカバーされていて、歌に込められた思いが、時代を超えて届く瞬間があるのではないかと感じます。聴くだけでなく、ギターで弾き語りできるところにもフォークソングの魅力がありますよね。
六角ギターを弾きながら歌えるのは、素晴らしいことですね。日本のフォークソングの良さって、みんなで歌えることなんじゃないかな。日本の戦後の音楽って、ハワイアン、ロカビリー、タンゴなど、いろいろありましたけど、難しいものが多いんですね。でもフォークは弾き語りができる音楽だから、みんなのものになっていったんですよね。たくさんの人が一緒になって歌って具現化できることはなんと素晴らしいんだろうと思います。
加藤小林亜星さんという作家がいらして、「酒は大関こころいき」の作詞・作曲者でもあるのですが、あの人が鉄則にしていたのは、伴奏なしで鼻歌で歌える歌じゃなければダメだったことでした。
六角寺内貫太郎さんですね(笑)。
加藤あの人が作ったのは、フォークではないけれど、フォークにも通じることだと思います。
六角『酒とつまみ編集部選・酒飲みソングちゃんぽん 天国までの百リットル』(2015年発表)というコンピレーションアルバムがあって、実は加藤さんの「酒は大関こころいき」と六角精児バンドの「お父さんが嘘をついた」という曲が入っているんですよ。植木等さんの「スーダラ節」も入っています。

──加藤さんと六角さんとの間では、そんな縁もあるということですよね。さきほど打ち合わせをされたとのことですが、どのようなコラボレーションになりそうですか?
加藤多分コラボする場面はたくさんあると思いますよ。「戦争を知らない子供たち」は一緒にやりますよ。もしかしたら、「帰って来たヨッパライ」もやるかもしれません。どうなるのか、想像がつきませんけど(笑)。
六角音楽もそうですが、この対談のようにMCでのコラボもあるんじゃないでしょうか。
──六角さんは、加藤さんとコラボレーションするのは、どんな気分ですか?
六角加藤さんと同じ空間の中にいて、加藤さんの力をいただければ、それで十分です。僕は加藤さんのパワーは音楽を通じて知ってはいるのですが、今回みたいに身近なところでそのパワーをもらえるのだから、こんな幸せなことはないです。ただし、ステージだと、客席にお客さんがいて、第三の目があるから、そこも気にしなければいけないですよね(笑)。
加藤第三の目って!(笑)。みなさん、第三の目になるために来てください(笑)。








