──六角さんは、フォークソングとの出会いはいつ頃、どんな曲ですか?
六角僕がいちばん最初に聴いたフォークソングは、ザ・フォーク・クルセダーズの「帰って来たヨッパライ」ですね。叔父さんが持っていたレコードを聴かせてもらいました。自分で最初に聴いたのは、小学校3年の時に、『ヤングスタジオLOVE』(TBSラジオ)というラジオ番組で流れていた六文銭の「雨が空から降れば」でした。
加藤私は激的に時代が変わっていく、その渦の中にいたじゃないですか。でも後から見た人は、全部が同じ嵐のように見えていたんじゃないですか?
六角もしかしたらそうかもしれないですね。ただ、様々に移り変わっていくフォルムは見えていました。僕の場合は、歴史を紐解くような感覚があったんですよ。1966年にマイク眞木さんの「バラが咲いた」と荒木一郎さんの「空に星があるように」があって、1967年にザ・フォーク・クルセダーズの「帰って来たヨッパライ」があり、1968年に高石ともやさんの「受験生ブルース」があって、中津川の『フォークジャンボリー』(1969年~1971年)が開催されて、1969年にエレックレコードが設立されて、といった感じで、歴史の流れを追うようなところはあったんじゃないかと思います。
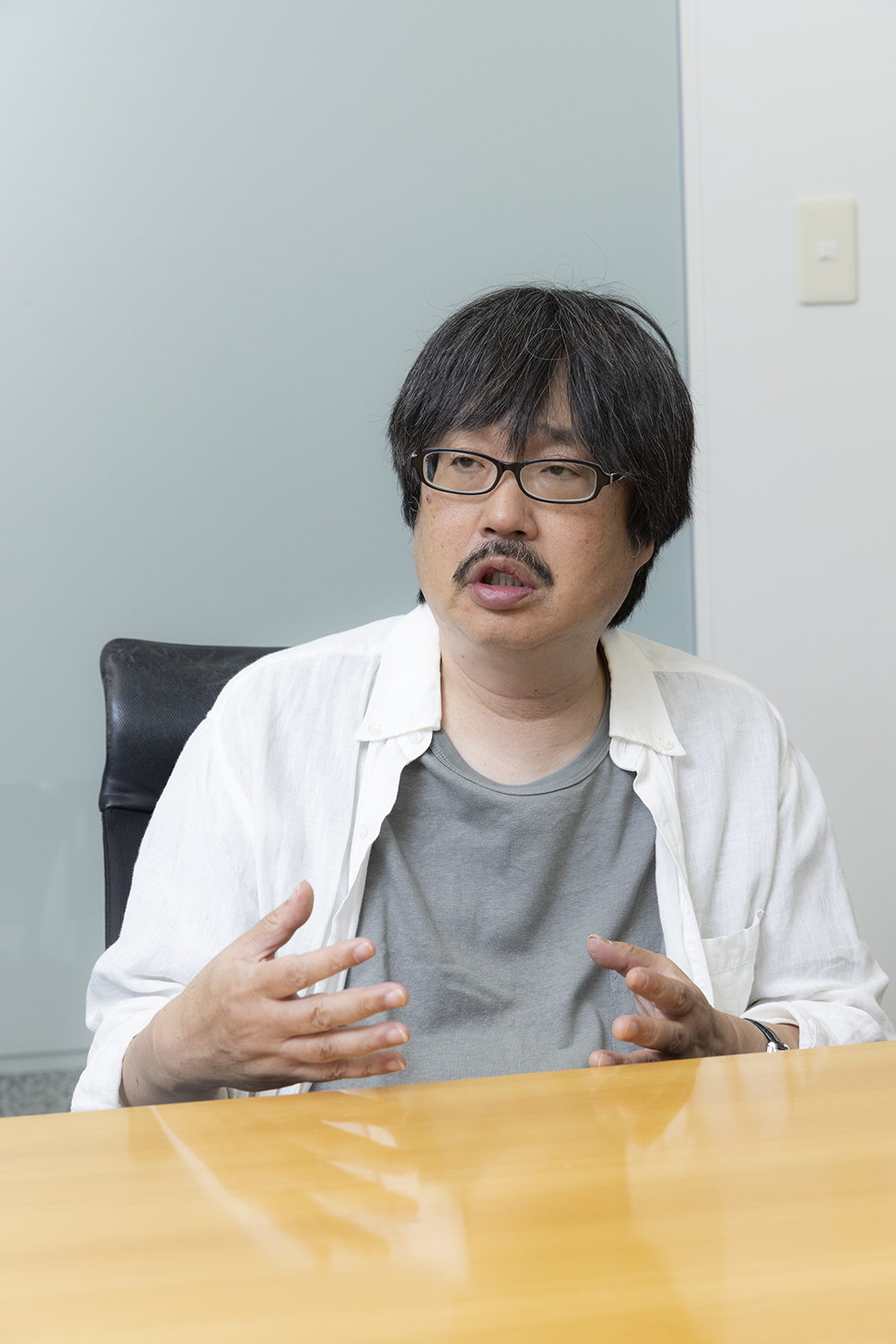
加藤今の視点で見ると、すべてが“フォークソング”という大きな括りとして見えているかもしれません。でも当時、リアルタイムで感じていたのは全員がバラバラで存在していたことですね。
六角そこが僕らにはわからないところですね。
加藤当時、あるテレビ番組でフォークの人たちを集めて、「最後に全員で歌ってください」という段取りになったんですが、「俺はあんな歌は歌いたくない!」「冗談じゃない!」と、一人ひとりの主張がはっきりしすぎていて、まとまらないわけ(笑)。そこが本当の意味での日本のフォークのおもしろいところですよね。
六角確かに皆さん個性的です。
加藤あの頃のフォークって、何もないところにボコボコボコッって出てきました。でも、それぞれの生まれた必然性は違うわけ。先日、NHKホールでの私のソロコンサートでも、「戦後80年、全部見てきてますよ」って話をしたんですね。でも、“実は何も見ていなかったのかもしれない”と思うこともあるんですよ。私がデビューした当時の話ですが、野坂昭如さんに初めてお会いした時に、野坂さんが「あんたは僕の妹だね」と言いました。後に、野坂さんの書いた『火垂るの墓』を読むと、兄が14歳、妹が4歳になるまで、終戦後の混乱期に必死で生き抜いた物語だったのね。それで、野坂さんが私のことを「妹だ」って言ってくれたのは、死んでほしくなかった妹の成長した姿を私に重ねてくれたからだと理解していました。でも最近になって調べてみたら、野坂さんの妹は終戦直後に1歳4か月で亡くなっているんですよ。
六角その部分はフィクションだったのですね。
加藤野坂さんは、妹をなんとか生かしておきたかったんだと思います。それで、せめて小説の中では妹が4歳になるまで自分と一緒に生きていたことにしたんでしょうね。その事実を知った時に、私は野坂さんの思いを正しく把握してはいなかったんだと思い知りました。妹を生かしておけなかった無念、後悔、贖罪の思いもあったはずですが、そこまで私にはわかっていませんでした。そのことと一緒で、戦争の悲惨な現場を体験した人たちが私たちの世代に託したことがあって、受け取ろうとしてきたけれど、受け取りきれていないものもあるんじゃないかと考えることがあります。1960年代はベトナム戦争があったので、反戦の思いを歌に託して、私たちなりに頑張りましたが、受け取ることとはそこで完結するものではないんですよ。

──そこで一人ひとりが受け取った思いが、1960年代末に生まれたフォークソングのムーブメントの原動力のひとつになっているということですよね。
加藤当時のフォークソングはかなりエッジが立っていましたが、そこで生み落とされたエッジは、若い世代に十分に伝わっていない部分もある気がしています。もちろん歌ですべてを伝えることはできませんが、今回のコンサートでも、そのエッジを少しでも伝えられたらという思いはありますね。
六角確かに1960年代をオンタイムで生活していた方の感覚は、我々には全部は伝わってこないんだろうなと思います。当時のフォークの人たちには、ルーツみたいなものがあって、高石ともやさんのように、ボブ・ディランやピート・シーガーなど、アメリカのフォークソングの影響を受けて、シンガーソングライターになった人もいました。フォーク以前には、作詞家と作曲家が流行歌を作って、歌手が歌っていた時代がありましたよね。

──ザ・フォーク・クルセダーズの「悲しくてやりきれない」は、作詞はサトウハチローさんですし、六文銭は谷川俊太郎さんが作詞された曲もたくさんあります。作詞家が“詩人”的に関わっていた作品が多いことも、当時のフォークソングの特徴のひとつですよね。
加藤なぜ北山修さんがサトウハチローさんに頼んだのだろうと疑問を抱いて、調べたことがありました。発注の経緯はわかりませんでしたが、サトウさんの伝記的な作品に、“この曲のメロディを聴いた瞬間に浮かんだのが、広島の空だった”という内容が書かれているんですよ。サトウさんの弟が広島で被爆して亡くなり、その弟の姿を探し歩いた時の広島の空が“あまりにも美しくて、悲しくて悲しくてしょうがなかった”と表現されています。その時の気持ちを歌にしたのが「悲しくてやりきれない」という曲です。当時のフォークソングには1曲ごとに物語があるのね。戦争が終わった時に10代半ばだった世代の人たち、サトウハチローや谷川俊太郎のパワーはとてつもないものがありました。私もそのパワーに殴られた一人です。そのパワーの激しさを受けとめようとすると、動き出さなきゃいけないという気持ちになるのね。そういう関係性が当時のフォークソングにとっては重要だったのだと思います。
六角戦争が終わった時に十代だった人たちのエネルギーをもらった世代が、そのエネルギーを音楽に転換していったのが、当時のフォークソングのムーブメントだったわけですね。
加藤ジャックスのような日本のロックも一緒ですよね。あの時代の人たちって、ドロドロとした沼のようなものが音楽活動のモチベーションになっていました。私はシャンソンからスタートして、その後、「ひとり寝の子守唄」のような自作曲をギターを弾きながら歌っていたから、フォークというジャンルの人と見られるようになったんですね。でも、私がフォークの世界に入っていけたのは、高石ともやくんが誘ってくれたからですね。高石くんが、「自分の作った曲を歌えばいいじゃない?」って言ってくれて、ジャックスとのセッションコンサートに呼んでくれたんですよ。それからフォークを語る資格のある人間になったのかもしれません。でも本当は、「おトキさん、ロックだよね」って言われるのがいちばん好きなんですけどね(笑)。

六角その場合のロックって、スピリットじゃないですか。フォークだとかシャンソンだとか、いわゆるジャンル分けとは違う根底に流れているものだから、ロックな人が歌ったら、ロックになるということですよね。
加藤その意味では、歌謡曲にだって演歌にだってロックなものはありますね。
六角ロックって精神だし、その精神が加藤さんにも流れているということだから、今回のコンサートでは、その“パワー”をいただけたらと思っています。








